外国人技能実習制度を活用する企業が増えるなか、現場で最も多く聞かれるのが「思っていたよりも意思疎通が難しい」という声です。
この記事では、技能実習生とのコミュニケーションで起こりやすい誤解やトラブルの傾向を整理し、現場ですぐに実践できるコミュニケーションの工夫、そして企業側の受け入れ姿勢について具体的に解説します。
実習生との信頼関係を築き、安全で前向きな職場づくりを目指す方のヒントになれば幸いです。
目次
技能実習生と起こりがちなトラブルとは?
技能実習生との間では、文化や常識の違いから予期せぬ誤解やすれ違いが生まれることがあります。
ここでは、現場でよく見られるトラブルの事例とその背景を解説します。
言葉は通じても、意図が伝わらない
技能実習生は来日前に日本語を学習していますが、実際の現場で使われる表現や専門用語、曖昧な指示は通じにくいことがあります。
たとえば、「ここ、よろしくね」といった指示は、日本人なら察して動けても、実習生には何をどうすべきか分かりません。
理解していないのに「はい」と返事をするのは、「分からないと言ってはいけない」と思ってしまう心理があるためです。
習慣や価値観の違いが摩擦を生む
時間の感覚や上下関係、職場での距離感、私語への意識、宗教的配慮など、多くの場面で文化の違いが表れます。
たとえば、数分の遅刻を許容する文化から来た実習生が、始業時間に1分遅れただけで叱責されると強いストレスを感じることがあります。
逆に、日本人社員側は「常識がない」と受け取り、評価を下げてしまうこともあるのです。
「冷たい」「馴れ馴れしい」のギャップ
フレンドリーな関係を望む実習生に対し、日本人側が一定の距離を取る対応をすると、「冷たい」「歓迎されていない」と誤解されることがあります。



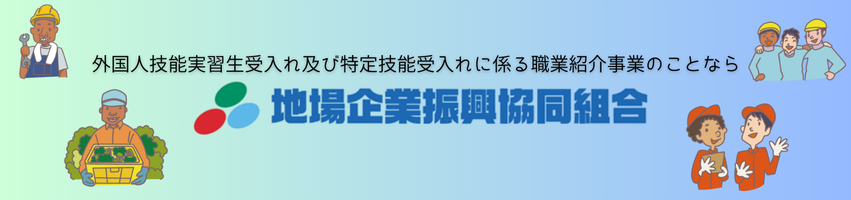



 コラム一覧に戻る
コラム一覧に戻る