技能実習 / 特定技能
技能実習から特定技能へスムーズに移行させる方法とは?
2025.07.04
人手不足が深刻化する中で、外国人材の確保・活用は多くの企業にとって重要な課題となっています。
なかでも「技能実習」から「特定技能」への移行は、すでに日本で一定期間就労経験がある人材を継続して雇用できる有効な手段です。
特定技能制度は、2019年に創設された新たな在留資格であり、制度開始から約6年が経過した今、技能実習からの移行者がその大半を占めています。
本記事では、企業の人事担当者が押さえておくべき「技能実習から特定技能へのスムーズな移行方法」について、制度の概要・要件・手続き・注意点までを網羅的に解説します。
出典:在留資格 特定技能・特定技能制度運用状況(令和6年12月末)
目次
技能実習と特定技能の違いとは?
技能実習から特定技能へ移行させるためには、まず両制度の目的や仕組みの違いを正しく理解することが重要です。
制度ごとの特徴を把握しておくことで、自社の受け入れ方針や人材育成の方向性も明確になります。
技能実習制度とは?
技能実習制度は、発展途上国の人材に日本の技術を移転することを目的とした制度です。
原則として1号(1年)、2号(2年)、3号(2年)の最大5年間、特定の作業に従事しながら技能を習得してもらう構成です。
制度上は「国際貢献」が目的とされており、実習終了後は母国へ帰国して技術を生かすことが前提となっています。
ただし、実際には人手不足を補う労働力として受け入れている側面も強く、待遇や労働環境をめぐって課題も指摘されています。
特定技能制度とは?
一方、特定技能制度は日本国内の人手不足に対応するために創設された制度です。
2019年4月に新設された在留資格「特定技能1号」により、一定の技能水準と日本語能力を有する外国人が、14分野(現在は16分野以上)で最大5年間の就労が可能となりました。
特定技能1号の在留者は、技能実習修了者に加え、試験に合格した外国人留学生なども対象となっており、企業との直接雇用が原則です。
さらに、熟練した人材は「特定技能2号」に移行することで在留期間の上限なく、家族帯同も可能となります。
両制度の主な違いまとめ
技能実習と特定技能は「外国人を受け入れて働いてもらう」という点では共通していますが、その制度目的や受け入れ条件、労働条件などには明確な違いがあります。
以下は、企業が押さえておくべき主要な相違点を整理した比較表です。
| 比較項目 | 技能実習 | 特定技能1号 |
|---|---|---|
| 制度目的 | 技能移転(国際貢献) | 人手不足の解消 |
| 在留期間 | 最大5年(1号〜3号) | 最大5年(1年更新) |
| 試験要件 | 原則不要(介護を除く) | 技能+日本語試験が必要(※一部免除あり) |
| 雇用形態 | 監理団体のもとでの実習 | 企業との直接雇用 |
| 転職可否 | 原則不可 | 同一分野であれば可 |
| 家族帯同 | 不可 | 2号に限り可能 |
特定技能の方が、就労の自由度やキャリア継続性が高く、企業にとっても長期的な人材確保につながる制度設計になっています。
特定技能への移行条件(資格・試験・在留資格)
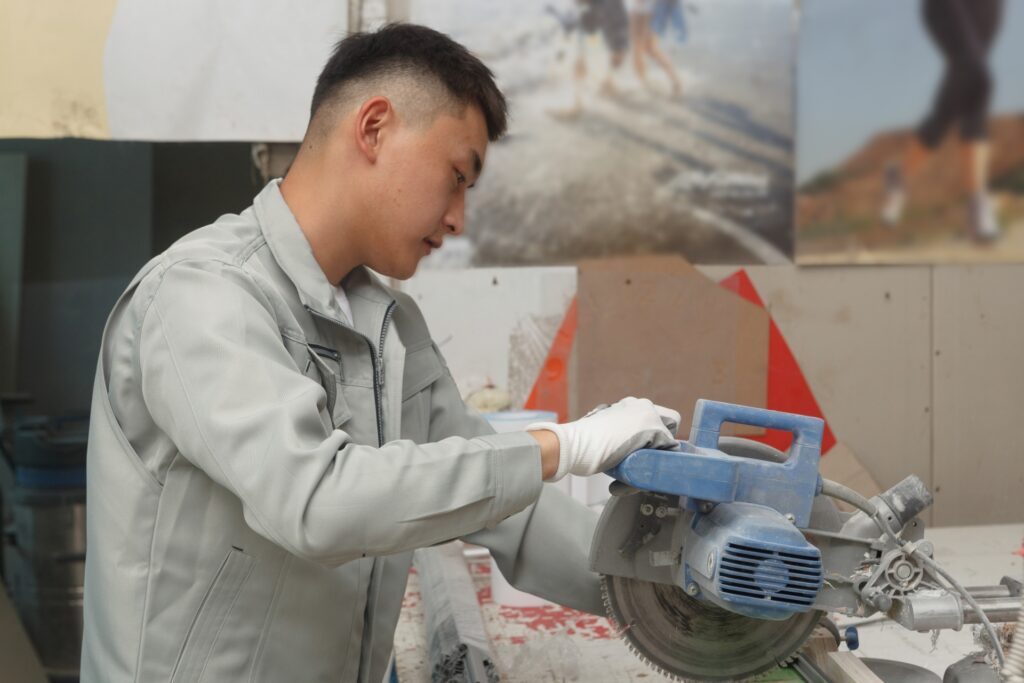
技能実習から特定技能へスムーズに移行するためには、制度上で定められた一定の条件を満たしている必要があります。
ここでは、企業の人事担当者が押さえておくべき「移行の要件」と「試験免除の仕組み」について詳しく解説します。
技能実習2号を「良好に修了」していること
特定技能1号に移行するには、まず「技能実習2号を良好に修了した実習生」であることが条件です。
「良好に修了」とは、実習期間中に重大なトラブルや失踪等がなく、所定の技能検定(随時3級や基礎級など)に合格し、監理団体から適切な修了評価を受けた状態を指します。
これは、「一定の技能水準を実務経験と評価試験によって証明できている」という意味でもあり、技能実習制度における一つの区切りでもあります。
※途中で実習を中断した場合や、評価が「不良」である場合は、特定技能への移行は原則認められません。
出典:外国人の方
同じ分野・職種であること
もう一つの大前提は、実習中に従事していた作業内容(職種)が、特定技能で受け入れ可能な分野と一致していることです。
たとえば、食品製造の実習生は「飲食料品製造業」の特定技能に移行できますが、「介護」や「外食業」など他分野の特定技能1号には移行できません。分野が異なる場合は、新たに技能評価試験の合格が必要です。
そのため、移行を見据える場合は、実習開始時点から「どの特定技能分野につなげられるか」を確認しておくことが重要です。
試験が免除されるケースも
通常、特定技能1号の取得には以下の2つの試験に合格する必要があります。
-
各分野ごとの「技能評価試験」
-
日本語能力試験(N4程度)
ただし、以下のように一部試験が免除されるケースがあります。
| 状況 | 技能試験 | 日本語試験 |
|---|---|---|
| 実習と同一分野に移行 | 免除 | 免除 |
| 実習とは異なる分野に移行(例:製造→外食) | 必須 | 免除 |
このように、同一分野での移行であれば、評価試験も日本語試験も不要です。
企業側の視点では、あらかじめ「移行できる職種か」「評価が良好か」を確認し、制度上スムーズに移行可能な対象者を見極めておくことがカギとなります。
移行プロセスのステップ(実務フロー)

技能実習から特定技能への移行を円滑に進めるためには、計画的な準備と適切な手続きが欠かせません。
以下では、実際のフローに沿って、企業が行うべき具体的なステップを紹介します。
① 本人の意思確認と社内方針の決定
まずは、技能実習生本人に特定技能での就労継続の意思があるかを確認します。
この段階で、以下を整理しておくと移行後のミスマッチを防げます。
-
特定技能で雇用する予定職種・勤務地
-
雇用条件(給与、休日、勤務時間など)
-
社内の支援体制の可否(登録支援機関に委託するかも含め)
② 技能実習の修了に向けた準備
技能実習2号を良好に修了するには、所定の評価試験への合格や、実習期間の満了が必要です。
監理団体と連携しながら、必要な試験を受けさせ、修了証明書の取得を目指しましょう。
この時点で、移行予定分野との整合性も再確認します。
③ 雇用契約の締結と支援計画の作成
特定技能1号の在留資格を取得するには、企業との間で新たな「雇用契約」の締結が必要です。
さらに、外国人への生活・業務支援を行う「支援計画」も必須です。企業が自社で支援を行う場合は、担当者の配置・記録の管理体制も必要となります。
対応が難しい場合は、登録支援機関への外部委託も可能です。
④ 在留資格変更の申請手続き
必要書類をそろえたら、管轄の出入国在留管理局へ「在留資格変更許可申請」を行います。
申請時に必要な書類の一例は以下のとおりです。
-
在留資格変更許可申請書
-
技能実習修了証明書
-
雇用契約書の写し
-
支援計画書
-
会社の登記簿謄本、決算書など
-
パスポート・在留カードのコピー
※必要書類は所属機関や分野などにより異なる場合があります。
申請から結果が出るまでは1〜2ヶ月程度かかることがあるため、在留期限の3ヶ月前までには準備を始めるのが理想です。
出典:在留資格「特定技能」
⑤ 特定技能としての受け入れ開始
在留資格変更の許可が下りると、特定技能1号としての雇用がスタートします。この段階で行うべき対応は以下のとおりです。
-
雇用保険・社会保険の手続き
-
特定技能外国人としての支援開始
-
管轄入管への定期・随時の届出準備
就労開始後も、労働条件・生活環境・支援実施状況などを記録し、適切に報告・保存する義務があります。
企業が注意すべきポイント(法的・実務的観点)
技能実習から特定技能への移行は、企業と外国人双方にとって制度的にも就労環境的にも大きな変化を伴います。
ここでは、法令順守と適切な雇用対応という2つの観点から、企業が押さえるべきポイントを紹介します。
雇用・契約に関する注意点
特定技能外国人を雇用する企業には、以下のような法的ルールの順守が求められます。
-
日本人と同等以上の待遇が必要
給与・手当・労働時間・福利厚生などにおいて、日本人と差のない条件であることが必須です。技能実習期間よりも責任が重くなるため、報酬面の見直しも必要です。 -
不適切な契約条件は禁止
違約金の設定、パスポートの預かり、転職の制限などはすべて禁止事項です。雇用契約書は、法務省のモデルなどを参考に適正に作成する必要があります。
支援・届出・定着に関する注意点
受け入れ後の支援や定着に関しても、以下のような実務対応が求められます。
-
1号特定技能外国人支援計画の実施義務
住居手配、生活オリエンテーション、日本語学習の機会提供、相談体制など、全10項目の支援を実施し、記録・保管する義務があります。 -
定期・随時の届出が必要
四半期ごとの就労・支援状況報告や、契約変更・終了時の届け出を怠ると、入管からの指導対象となる可能性があります。 -
定着支援が離職防止のカギ
特定技能は転職が可能な制度であるため、「ここで働き続けたい」と思ってもらえる環境づくりが欠かせません。キャリアパスの提示、職場内のコミュニケーション支援、多文化理解の促進が重要です。
スムーズな移行を実現するための実践ポイント
技能実習から特定技能への移行を成功させるには、制度理解に加えて、企業側の段取りや本人との信頼関係づくりが欠かせません。
以下では、現場で実践されているポイントを整理します。
早めの意思確認と試験対策の支援
特定技能への移行には、技能評価試験や日本語試験(原則N4程度)が必要なケースもあるため、実習期間中から試験準備をサポートする体制づくりが重要です。
過去問や教材の提供、勉強時間の確保など、実習中のサポートが合否を左右します。
また、本人が「この会社で働き続けたい」と思っているか、早期の意思確認も欠かせません
。将来的な待遇や業務内容を共有し、継続雇用への意欲を引き出すことがポイントです。
在留期限と社内体制の管理
移行のタイミングを逃さないためには、在留期限の3~4ヶ月前から申請準備に着手するのが理想です。
申請の遅れや書類の不備があると、在留資格の空白を避けるために特定活動ビザでつなぐ必要が出てくる場合もあります。
さらに、外国人材の在留情報を管理する社内リストを整備し、更新・届出のスケジュール管理をチーム内で共有するなど、計画的な体制づくりが定着率にもつながります。
まとめ|制度の理解と計画的な移行体制が鍵

技能実習から特定技能への移行は、外国人材を段階的に育成し、企業の将来的な中核戦力として活用していくための有効な手段です。
一方で、特定技能の受け入れには、在留資格変更の手続きや支援体制の整備、法令順守といった多面的な準備が求められるため、計画的な対応が不可欠です。
こうした背景を踏まえ、制度の活用を検討する企業にとっては、外国人受け入れの支援に実績のある監理団体・支援機関と連携することが、スムーズな制度運用と定着促進に効果的です。
たとえば、地場企業振興協同組合では、インドネシア・ベトナム・スリランカ・中国などの国際基準に沿った送り出し機関と提携し、外国人技能実習生の受け入れから特定技能への移行支援まで、一貫した体制で対応しています。
現地での事前教育、日本での生活支援、配属後の定期フォローに至るまで、きめ細かな支援を通じて企業の人材活用をサポートしています。
とくに、技能実習制度と特定技能制度の双方に対応可能であることから、「まずは実習で育て、適性があれば特定技能へ」という段階的な外国人雇用にも柔軟に対応できる点が特徴です。
今後、外国人材の活用を中長期的な戦略として検討する企業にとって、こうした支援機関の活用と制度への理解を深めることが、安定的な雇用と戦力化への第一歩となるでしょう。
RELATED関連記事

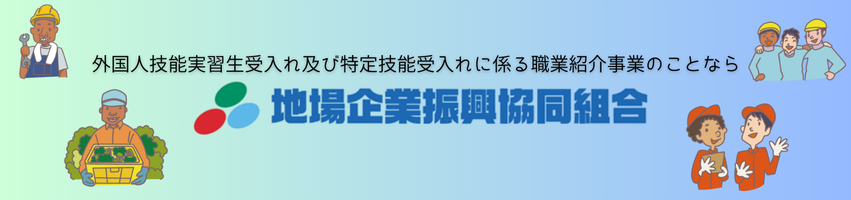



 コラム一覧に戻る
コラム一覧に戻る